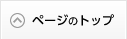教育サポート書籍

わたしを語ることばを求めて 表現することへの希望
牲川波都季 細川英雄 著
定価(本体2,200円+税) 四六 304頁 978-4-385-36198-7
2004年3月30日 発行[品切れ]
早稲田大学本庄高等学院三年生の「日本語総合」の授業実践と観察の記録。授業担当者、観察者である著者、生徒が、内省と他者と関わることを通して「わたしのことば」を獲得していくドキュメント。
本書は、早稲田大学本庄高等学院三年生の「日本語総合」の授業実践と観察の記録である。日本語教育研究者・細川英雄と牲川波都季と14名の生徒が、他者との真摯な関わりを通じて「わたしのことば」を獲得していくドキュメントである。
・高校生たちが私に教えてくれたのは、表現することの困難と希望の中で、ある時はしたたかに、ある時は他者の表現に揺るがされながら、「わたし」を表現することの希望だった。(牲川波都季)
・「わたしのことば」で表現する自由のためには、学習者一人ひとりの「個の表現」というものを保障することと同時に、「教室」というコミュニティーの中で、共同体メンバーとしての他者との関係をつくることで、権力としての規範から解放されなければならない。(細川英雄)
著者略歴
牲川 波都季(せがわ はづき)
1974年富山県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。
現在、早稲田大学日本語研究教育センター助手、早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程在学。
主要論文として、「学習者主体とは何か」(細川英雄編『ことばと文化を結ぶ日本語教育』凡人社2002)、「相互評価システムに対する学習者の意識──高等学校における<日本語表現>受講者へのインタビュー調査から」(『早稲田大学日本語研究教育センター紀要』16、2003)、「日本語教育学における「思考様式言説」の変遷」(『日本語教育』121,2004)などがある。
ウェブサイト:http://www.ne.jp/asahi/net/jpn/segawa/kenkyu/index.htm
細川 英雄(ほそかわ ひでお)
1949年東京都生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(教育学)。
現在、早稲田大学大学院日本語教育研究科教授(言語文化教育論)主要著書として、『パリの日本語教室から』(三省堂1986)、『日本語教育と日本事情―異文化を超えて』(明石書店1999)、『日本語教育は何をめざすか―言語文化活動の理論と実践―』(明石書店2001)、共編に『「総合」の考え方と方法』(早稲田大学日本語研究教育センター2003)『国語表現Ⅰ・Ⅱ』(三省堂2003・2004)などがある。
ウェブサイト:http://www.f.waseda.jp/hosokawa/
目次
わたし自身の旅―まえがきに代えて…細川英雄…2
第一章 「わたしのことば」で表現することの意味…細川英雄…13母語の主体化
「わたしのことば」とは何か
自分の「考えていること」を表現する教室
「日本語表現総合」の試み
教室で教師は何をするのか
「わたしのことば」で表現することの意味
世界の回復に向かって
第二章 わたしを語ることばを求めて…牲川波都季…37
はじめに…38
「日本語表現総合」のあらまし
私はどこに立っているのか
観察記を書くにあたって
Ⅰ 〈総合〉を知る…46
第一回 (四月一一日)「表現の扉をひらく」 46
目標にとまどう学習者たち自己紹介と決意表明
第二回 (四月一八日)誰にインタビューしよう 55
不意打ち自分を始点に語りだすことから誰にインタビューしよう厄介な質問「日本の教育についてどう思いますか」なぜ動機固めにこだわるのか動機にはエピソードを記録を残す意味
Ⅱ テーマと動機を固める…68
第三回 (四月二五日)インタビュー対象の決定 動機メモを書く 68
「わたし」一人にとっての動機動機メモを作る対象を選ぶさまざまな動機
第四回 (五月二日)動機の下書きを話す 76
「変」かつ「冷静」な富岡先生「僕に聞かないでください」「偏見」どおりのラリーさん「日本人らしからぬ国際感覚」とは何か強固なステレオタイプをめぐって一般的な日本人ってどこにいる?「正しい表現」へのこだわりインタビューの肝
第五回 (五月九日)動機を書く 102
面識のない人を選んだ二人ステレオタイプに陥らないためには「正しい表現」に対する学習者の本音インタビューを始める日程や書く分量はいい加減でいい
Ⅲ インタビューする…114
第六回 (五月一六日)インタビューの報告① 114
インタビューの実際――滝田先生の「淋しさ」何をインタビューから引き出すのかインタビュー記録から知ることばのゆるやかさ混乱してもいい?「みんなで評価をつける。そういうコンセプトです。」
第七回 (五月二三日)インタビューの報告② 127
怒らない嶋川先生今まで知らなかったあの人の一面議論低迷
第八回 (五月三〇日)インタビューの報告③ 135
逃げてしまった本木ないものねだりで終わらないために目次を作り始める「公開」で評価?
第九回 (六月六日)インタビューの報告④・下書き一回目の報告① 147
録音に失敗!インタビュー結果いろいろインタビュー記録を忠実に写せばよいのか
Ⅳ レポートを書く…153
第10回 (六月一三日)インタビューの報告⑤・下書き一回目の報告② 153
レポートの評価ポイント付け加えられた「深いところ」インタビューを生き生きと再現するインタビューの信憑性を高める工夫細川に影響を与えた堤
第11回 (六月二〇日)下書き一回目の報告③・下書き二回目の報告① 166
オリジナリティとは何か一般論なんていらないことばのかなたに何を見ることができるかラリーさんの内面を見つけ出す
第12回 (六月二七日)下書き一回目の報告④・下書き二回目の報告② 180
語り合うことで生まれた新しい何かレポートの山場はどこにアドバイスの受け取り方は一直線ではない一般論から離れるオリジナリティを求める声ぞくぞく強烈な「正しい表現」の縛り「正しい表現」の縛りがゆるむとき「雲のような存在」の人との出会い
第13回 (七月一一日)最終レポートの提出 204
レポートが出揃った!相互自己評価の手順「一点刻みの成績はめんどくさい」の真意〈総合〉後期の活動
Ⅴ 相互自己評価…216
第14回 (七月一八日)相互自己評価会 216
表現のとびらは全員がひらくコメントの実際オリジナリティが大切二つのオリジナリティその人なりのオリジナリティそれぞれの歩みを評価自分で作品を振り返る厳しい批評も受けとめて初めてやって来た生徒からのコメント他者と向かい合うために
終わりに―表現することへの希望…246
疑い晴れて
成功までの歩み
主人公の転換
私と〈総合〉
付録 相互評価システムに対する学習者の意識…牲川波都季…255
―高等学校における〈日本語表現〉受講者へのインタビュー調査から―
あとがき…牲川波都季…297
わたし自身の旅――まえがきに代えて
細川英雄
私は常日頃、自分のことばで語りたいと願っている。一人ひとりの顔を持った、個性にあふれた意見の交換によって、実のあるコミュニケーションを行い、ここにいてよかったという実感を他者と共有したいと思っているからだ。
しかし、「わたしのことば」で語るという行為を実現させるために、マニュアルのようなものが用意されているわけではない。
たとえば、教室の活動一つを考えても、自分のことばで語りたいという生徒一人ひとりの願いは、どのようにして実現することができるのだろうか。そして、「わたしのことば」で語るという行為を実現させるために、何をどのように考えたらいいのか。
このテーマのために、ここでは次のような手順を踏んで考えてみようと思う。
まず、「わたしのことば」とは何か。
次に、その「わたしのことば」で語るとは何か。
そして、そのための具体的な方策はどこにあるのか。
この問題は、大きくいえば、母語としての国語と第二言語としての日本語を結んで言語教育全体を志向することであり、また、教室を学習と教育の交差する学びの場の創造として捉えることであり、そして、ことばと文化の共生の課題を、具体的な意味のあるコミュニケーション活動として捉えなおすことでもあるはずだ。
では、どのような教室が、どのようにして可能なのか。それぞれの学習者への支援やクラスの組織化等を通して、教師は学習者の何をどのように育成すればよいのか。
この問題の発見と解決が、ことばの教室の、そして、ことばの教師の課題だろう。
*
このようなことを考えるようになるまでに、私は、ずいぶん回り道をしてきたような気がする。
私は、大学で国語学を学んだ。単にことばに興味があったから、というのがその選択理由だが、当時の私には、ことばを研究するということと自分の将来とがどのようにつながるのかが皆目わからなかった。だから、「何もしない」という無為徒食のための大学院時代は、長く暗いトンネルのような執行猶予期間だった。しかし、ここで得たものは、ことばに即して考える、という徹底した合理主義だった。
私の教育体験は、中学・高校の国語教員の後、国語学担当として教員養成に関わることからはじまったが、そこで最初に出会ったのは、いったい、国語教育はこれでいいのかという違和感だった。
実態に即してことばを構造的に考えるという姿勢から見ると、当時の私が関わった国語教室は、あまりにも閉塞した、心情かつ表現内容主義一色であり、ことばの構造への視点が欠落していたといってよい。
しかしながら、そうした国語教育を正面から批判するほどの度胸もなく、また、自分の研究その他においていろいろな意味で不安と自己嫌悪が混在する現実の中で、しだいに外国人のための日本語教育の理論に傾斜していったのは八〇年代初めごろのことである。
そのころ、ヨーロッパで日本語を教えてみないかという誘いがあり、一年間、フランスで日本語を教える機会に出会ったのは、今から思うと幸運だった。この一年でどれだけ多くのことを学んだだろう。
フランスからの帰国後、もはや当時の職場で自己実現していくことは不可能だと悟り、私は、他大学の「日本語・日本事情」担当に転出した。それからずっと日本語教育に関わってきて早二〇年になる。
ところが、日本語教育の世界に飛び込んで最初に出会ったのは、日本語教育の世界の中でおまけのように付随する「日本事情」という分野だった。いわゆることばを教えるということに対して、文化を教えるという分野なのだが、その「日本事情」という分野は、何を教えるのか、どのように教えるのかも皆目わからない、何でもありの世界、まさに混沌の坩堝だった。
しかし私は、その混沌性ゆえに、当時の日本語教育関係者の多くが好んでは足を踏み入れようとしないこの領域に、あえて関わることでまた、今度は日本語を構造的に考え、その仕組みを教えるという教育からハミダシてしまったのだ。
それは、むしろ混沌の坩堝としての「日本事情」の魅力だった。そして、その「何でもあり」のダイナミズムの立場から、現在の日本語教育はこれでいいのかというように、いつのまにか日本語教育の、ちまちまとした表現形式主義への批判論も書くようになっていた。
ふと気づくと、自分がどうしても入っていけなかった表現内容主義に対する疑問と、日本語教育の表現形式主義への批判との、ちょうど中間に立って両方に石を投げるというようなことをはじめている自分がいた。
そうした中で、かつて母語としての国語教育に関わった時に、どうしても馴染めなかった「わたしを語る」とか「自己をひらく」とかいう、そういう表現の意味は何だろうか、というようなことを考えはじめていた。
もう一度、その「わたし」というところに帰ってみようか、それを第二言語としての日本語教育に取り入れたならば、現在の言語教育にない、新しい視点を得ることができるのではないか。それはつまり、心情や表現内容を問題にする学習でもなく、また、表現を外側からだけ見るのでもなく、人間の思考と表現を結ぶプロセスそのものを考えることを目的とする、いわば第三の言語教育への道を切り拓くことはできないだろうか。
こんなことを考えていた矢先に、早稲田大学本庄高等学院で文章表現を教えてみないか、という話があったのは、まさに偶然としか言いようがない。この「日本語表現総合」というクラスをつくってみることで、もしかしたら第三の言語教育への試みができるかもしれない。この思いが、この本のもとになる教室を、自ら始めることになったきっかけである。
この本に描かれた教室で、生徒たち一人ひとりが自分のことばを取り戻す現場に立ち会い、「わたしのことば」で表現することの意味とその方法について学習の現場に即して具体的に考える、という僥倖にめぐりあった。
本書の第二章は、共著者である牲川が、このクラスの実際の活動を観察記の形で記したものである。そのクラス実施に当たっての構想及び授業担当は細川であるが、授業の記録・文字化作業、分析と執筆はすべて牲川が行った。
この観察記から、改めて自らの言動を振り返ることができ、第一章の理論概要をまとめることができた。学部時代からしたたかな叛骨の姿勢を示しつつ、歴史学の薫陶を受けて精緻な観察・分析の眼を持つに至った若き教育研究者の仕事に敬意を表したい。
あとがき
本書は、第一部で、「わたしのことば」で表現するための教室活動の理論を示し、第二部で、その理論から生み出された「日本語表現総合」の実際を記したものである。
第二部の観察記は、二本の論文-「表現の扉をひらく--早稲田本庄高等学院『日本語表現総合』(二〇〇〇年度一学期)の試み」(二〇〇一年『早稲田教育評論』一五(一))と「『日本語表現総合』と相互自己評価」(二〇〇一年『早稲田本庄高等学院 研究紀要』一九)の牲川執筆部分を下敷きにして書いた。また、〈付録〉は「相互評価に対する学習者の意識--高等学校における〈日本語表現〉受講者へのインタビュー調査から」(二〇〇三年『早稲田大学日本語研究教育センター紀要』一六)の転載である。
私には、当時自分の所属していた大学院のゼミで、はじめの二本の論文について報告する機会があった。
このとき、一番うれしかったことは、当時指導教授だった安丸良夫先生や他のゼミ生たちが「こんな授業がもし昔あったら、自分も受けてみたかった」と言ってくださったことである。私が感じた〈総合〉の魅力と可能性が、尊敬する先生やゼミ仲間たちに伝えられたことに小躍りしたことを覚えている。
その一方で、ゼミの友人たちからは、さまざまな批判のことばも投げかけられた。特に、ある友人からの、「教室空間には常に権力関係が内在する」という指摘は、この〈総合〉の実践は、担当者の教育方針を超えるための教育という、決定的な自己矛盾を孕んだものなのではないかという問いを私に抱かせた。
しかし、本書を書き終えて思うことは、ある学習者にとって、〈総合〉が教室空間の内側からそれを突き破って外に出て行く、一つの通路を押し開くきっかけになったことは確かなのだということである。
〈総合〉が終わってから一年以上がたとうとしているとき、私は先に挙げた拙稿を〈総合〉の元受講生たちに送った。それを読んで、今、大学でアカペラのサークルに熱中しているという真田から、こんな感想が届いた。
僕は最後の授業で、「自分は何?」っていうことを考える発展性のある授業だった、って感想文でだしたんですけど、「自分は何?」もあるんだけど、やっぱり歌の奥深いところにチャチャをいれたがっている自分の原点があそこだったと振り返って思います。(中略)日本語表現の授業がなかったら、全くいまの自分はないんですね。まぁ、他の授業とってたらそれはそれでまた違う自分もいるんだろうけど、いい意味でちょっと変な奴と思わせる部分を作らせた根はあそこだったなと。
振り返ると、自分の今のルーツは〈総合〉にあるのだと彼は言う。学習者によって〈総合〉で得たものには大きな隔たりがあるだろうが、少なくとも一人の学習者にとっては、自分の今を見つけていくきっかけになった。そのことの価値は誰にも消し去ることはできないと思う。
問いの全てに応答はできなかったが、ゼミでもらったさまざまな意見に背を押されて、私はこの観察記を書きつづけることができた。日本思想史というゼミにはまったく不似合いな報告に対し、率直な意見をくださった安丸良夫先生とゼミの友人たちに心から感謝したい。
そして、細川英雄先生が、〈総合〉にティーチング・アシスタントとして来てみないかと誘ってくださらなければ、本書を書くことはありえなかった。〈総合〉では、細川先生に、不可思議な魅力のつまった教育現場をあますところなく見せていただいただけでなく、本庄から大学へ帰る道すがら、ファーストフードをむさぼりながら、〈総合〉の意味や問題についての熱い思いをうかがうことができた。そのときに交わした意見が、本書や私ののちの論文を有形無形に支えている。
また、早稲田大学本庄高等学院の吉田茂さんには、実践当時にお世話になっただけでなく、本書に登場される先生方への連絡を取り次いでいただくなど、刊行のために大変お世話になった。
膨大な第一稿を読んで、焦点の絞り方を助言してくださったのは、三省堂国語教科書編集部の高橋正積さんである。同じく三省堂編集部の中村純さんには、刊行が決まってからの異常に忙しいスケジュールにも関わらず、本書の位置づけを問い直すようなアドバイスを幾度となくしていただいた。
体力と気分と文章のもちなおしに協力しつづけてくれた同居人の谷岡慶さんには、今、感謝のことばしか浮かばない。
最後に、〈総合〉を選び、出版にあたって引用を快く承諾してくださった元受講生のみなさん、あなたがたのおかげで本書は生まれました。あの語り合いの中にあって、一人黙々と記録していた私は、全くの半端な存在だったと思います。その私が、授業から三年も過ぎた今になって、こうした膨大な観察記録を書き上げたことを、みなさんは不思議に思うかもしれません。けれども、私にとってあのクラスは、その記憶をなんとか残しておきたいと思わせるほど衝撃的なものでした。
みなさんにとっては、本当はこんなこと考えてなかったとか、書いてほしくなかったとか、いろいろと不服な面もあると思います。それでも、みなさんの話や書いたものと私なりに向き合った結果なので、どうぞ大目にみてください。そして、いろいろな顔を見せ、私を驚かせてくれたみなさんがいなければ、本書は永遠に生まれませんでした。本当にありがとう。
二〇〇四年一月二五日 牲川 波都季
なお、本書は、二〇〇三年度早稲田大学学術出版補助費を得て刊行されるものである。
強固なステレオタイプをめぐって (本文の一部より)
このあと、細川が「どうでしょう」とほかの学習者に問い掛けると、児玉は、
児玉 これはこのままでいいと思うんですけど。前に、「我が家に招待すると言い出したときには、正直驚いた」って書いてあるし、文章でたぶん俺も外国人の前では引いてしまうってことを、みんな思ってると思うんで、俺はこのまま、説明しなくても、すっと理解できました。
という、上野に賛成するような意見を出した。外国人の前では引いてしまうのが日本人と「みんな思ってる」こと、それこそがステレオタイプを生み出す元凶なのだが、「みんな思ってる」から問題ないと児玉は言う。この児玉は、上野の前の別の学習者の動機には、ステレオタイプな枠組みを考え直させるような質問をしていた。だから私は、児玉は「らしさ」に疑いを抱いているのだと思っていた。ところが、上野に対する今回の意見では、「日本人らしさ」に何も疑問を感じていないようだった。そしてこの児玉の意見が引き金となり、細川から猛烈な反論が繰り出された。
細川 日本人だと外国人の前で、みんな引いてしまうんですか。
上野 (笑)
二、三人 (笑)
細川 そんなことは誰が決めた?
上野 はい?
細川 そんなことは誰が決めたんですか。
上野 いやまあ、これも偏見です。
細川 (笑)
「そんなことは誰が決めた?」という細川のことばには凄みがあり、声を荒げていたわけではなかったものの、私にはかなりの怒りが感じられた。上野やほかの数名は「日本人だと外人の前で、みんな引いてしまうんですか」との細川の問いに笑っていたけれども、〈総合〉では、こうした思い込みは笑い事ではすまされない。細川は、自分の声音の苛立ちに気づいたのか、上野の返答のあとには笑みを浮かべてみせたが、私の席からは、その笑顔が引きつっているように見えた。
なんとなく日本人とはこうだと思い込んでいることが、他者をそういうありきたりな枠に押さえ込むことになるし、また自分自身をも日本人の中に小さく収めてしまうことになる。ステレオタイプに対するこうした問題意識は、細川の留学生に対する実践でも一貫して見られるものだ。
留学生は日本にやってきて、そこで日本と自分の国との文化の違いを見つけ、だから日本人はいいとか、だから日本人はだめだとか、かなり単純な文化理解をすることがある。細川が留学生対象の日本語教育で求めてきたのは、もっと目の前の人や出来事と向かい合い、そうした個々の場面を自分なりに見つめていく能力を育てることだと私は理解している。だから〈総合〉でも、一瞬ぎょっとするほど強い口調で、上野に問うたのだと思う。
続きはこうだ。
上野 ただまあ、うちは文章の中でも書いてあるんですけど、母親は、中学校の保健の先生をやっていて、母親の中学校にやってくるAETの先生を、ことごとく我が家に招待してて、話を聞いていると、ほんと日本人は英語能力の問題じゃなくて、全然話しかけてくれないとか、英語の先生であっても、AETに話しかけてくれないっていうことも、俺は何度も聞いているし。
細川 お母さんから?
上野 いえ、AETの人から。
細川 あ。AETの人から。
上野 まあ、母親からも聞いてますけど。
細川 うん。
上野 だからそれに関しては俺は、もちろんそうじゃない人もいっぱいいると思うんですけど、俺はこれは正しいと思ってます。
上野は、母親やラリーさんからの話を総合して、日本人の国際感覚のなさについては「正しいと思って」いる。
- 三省堂教科書
- 国語教科書
- 国語教育情報:サポート書籍
- 『わたしを語ることばを求めて 表現することへの希望』